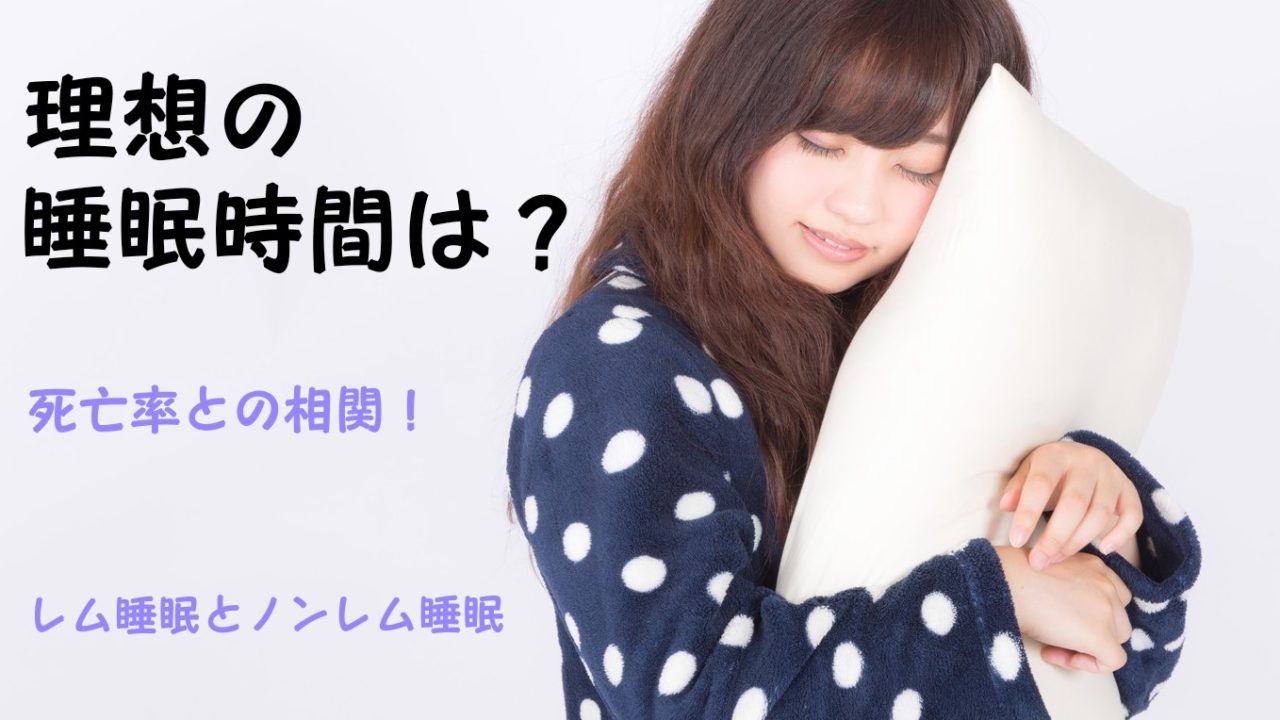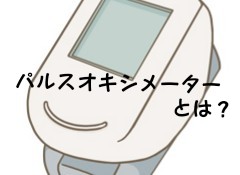睡眠時間は、人の健康に大きく関わっています。
睡眠時間が少なすぎても多すぎても、健康に良くないと言われています。
では、実際どのくらい睡眠をとると良いのでしょうか。
あまり寝なくても大丈夫な人、寝たいけど忙しくて時間がない人、いくら寝ても寝たりない人。
人によって睡眠時間はバラバラですが、実は理想とされている睡眠時間があります。
今回は、その理想の睡眠時間についてご紹介していきます。
睡眠とは
私達人間は健康な生活を送る上で、食事や運動と同じくらい睡眠は欠かせないものです。
睡眠は簡単に言えば、『眠る』ことです。
難しく言えば、『意識を喪失した生理的な状態』です。
人は基本的には夜に眠り、朝や昼は活動的になっています。
睡眠をとることで、身体の休息や成長の促進、怪我や病気の治癒の促進にもなります。
レム睡眠とノンレム睡眠
睡眠中は、レム睡眠とノンレム睡眠という状態が反復しています。
レム睡眠は『浅い眠り』、ノンレム睡眠は『深い眠り』です。夢はレム睡眠のときに見ていることがほとんどです。
レム睡眠とは
レム睡眠は英語でrapid eye movementsと言い、訳すと急速眼球運動という意味になります。また、rapid eye movementsの頭文字をとってREMすなわちレム睡眠と言われています。
寝ているときにまぶたの下で眼球運動が起こっていれば、レム睡眠ということになります。レム睡眠中は、身体は休んでいるのですが脳は活動しています。
ノンレム睡眠とは
ノンレム睡眠はnon REMということで、急速眼球運動を伴わない睡眠状態です。
レム睡眠よりも深く眠っている状態で、脳が休んでいる状態となります。
眠った直後はこのノンレム睡眠となり、その後はレム睡眠とノンレム睡眠が周期的に繰り返し起こります。
深い眠りのときに、成長ホルモンの分泌や体組織の修復などが活発になります。
理想の睡眠時間
睡眠には浅い眠りと深い眠りがあることがわかりましたが、何時間寝ると最も良いとされているのでしょうか。
よく言われているのは、『理想とされる睡眠時間は7時間』です。
睡眠不足ではダメですし、反対に睡眠過多になっても良くありません。
各国で睡眠時間と死亡率の相関の研究がされていますが、実際に睡眠時間が7時間の場合では死亡率が最も低いという結果が出ています。
睡眠時間が長い人でも短い人でも7時間の人に比べると死亡しやすいことがわかりました。その程度は、4時間未満(4.4時間まで)の睡眠時間では、男性で1.62倍、女性で1.60倍、また10時間以上(9.5時間以上)の場合には男性で1.73倍、女性で1.92倍となりました。
出典元:睡眠時間と死亡との関係|JACC Study(https://publichealth.med.hokudai.ac.jp/jacc/reports/tamaa1/index.html)
上記引用文は日本で行われた研究なのですが、その他にも各国で睡眠時間と死亡率の相関のたくさんのデータが発表されています。
各研究を見ていると、やはり『睡眠時間は7時間』が最も良いようです。
睡眠不足が良くない理由
睡眠不足の状態を続けていると、身体に様々な悪影響を及ぼします。
- ストレス増加
- 集中力低下
- 血圧上昇
- 頭痛
- 免疫力低下
- 新陳代謝低下 など
睡眠不足になると病気になりやすいだけでなく、疲労感が残り、仕事や日常生活にも支障を来たします。
また、睡眠不足では集中力が低下し、車などの乗り物の運転中には睡魔に襲われ事故に合う危険も高くなるので注意が必要です。
まとめ
人には欠かせない睡眠なのですが、研究データを見る限りでは理想の睡眠時間は7時間であることがわかります。
そのため、1日の約1/3の時間を睡眠に費やす必要があります。
当然睡眠だけでなく、食事・運転・喫煙・飲酒・ストレス・病歴・年齢などによって、死亡率は異なってきます。