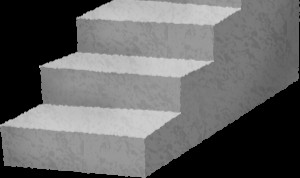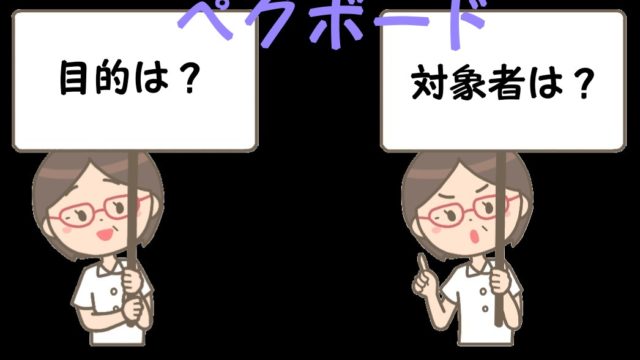杖を使った歩き方には3動作歩行や2点1点歩行などがあり、片麻痺患者もこの歩き方が基本となります。

片麻痺の場合、杖は非麻痺側(健側)で持ち、
- 杖
- 麻痺側(患側)
- 非麻痺側(健側)
の順序で下肢を出していきます。(3動作歩行)
もしくは、
- 杖と麻痺側(患側)
- 非麻痺側(健側)
の順序で下肢を出していきます。(2点1点歩行)
このように、歩行時には麻痺側の下肢が後ろに残らないようにする必要があります。麻痺側下肢の安定性を高くするために、杖を前に出した後に、もしくは杖と同時に麻痺側下肢を振り出します。
しかし、この下肢を振り出す順序には例外があります。それは階段の昇り降りをするときです。
階段昇降時には、歩行時とは異なる下肢を出す順序となります。
今回は、片麻痺患者が階段昇降動作時に下肢を出す順序についてご紹介していきます。
ちなみに麻痺のあるほうが麻痺側、麻痺の無いほうが非麻痺側となります。
片麻痺患者が階段昇段時に下肢を出す順序
片麻痺患者が階段を昇る際には、
- 杖
- 非麻痺側(健側)
- 麻痺側(患側)
の順序で下肢を出していきます。階段昇降動作は歩行動作よりも難易度が高く、転倒リスクも高くなるので基本的には3動作で行います。
杖の後に非麻痺側下肢を出すことで、後ろに残った麻痺側下肢の支持期(非麻痺側を振り上げるとき)には杖で補助が出来ます。さらにその後、麻痺側下肢を振り上げるときにも杖で補助が出来ます。
また、3動作で階段を昇る際には、先に振り上げた下肢を軸にして体重を前上方に持ち上げる必要があるため、相当な筋力がいります。そのため、非麻痺側下肢から振り上げていきます。
麻痺側下肢から振り上げてしまうと、体重を持ち上げることが出来ずにバランスを崩しやすいです。さらに体重を持ち上げきれずに非麻痺側下肢を振り出すと、つま先が段差に引っ掛かってしまうので大変危険です。
片麻痺患者が階段降段時に下肢を出す順序
片麻痺患者が階段を降りる際には、
- 杖
- 麻痺側(患側)
- 非麻痺側(健側)
の順序で下肢を出していきます。杖を出した後に、麻痺側下肢、最後に非麻痺側下肢を振り出します。階段昇段時とは下肢を出す順番が反対になります。
階段を降りるときには、後ろに残る下肢に相当な筋力が無いと反対側の下肢を振り出せません。そのため、筋力が十分にある非麻痺側下肢を後ろに残し、麻痺側下肢を先に振り出します。
麻痺側下肢を後ろに残し、非麻痺側下肢を先に振り出してしまうと、バランスを崩したり膝折れが起こりやすく転倒のもとになります。

おわりに
片麻痺患者の階段昇降動作は、歩行動作よりも転倒に注意しなければなりません。
昇段時には身体能力の高い下肢(非麻痺側)から、降段時には身体能力の低い下肢(麻痺側)から振り出します。
階段に手すりがついていれば無理をせず、杖ではなく手すりを使用して安全に階段の昇り降りを行いましょう。