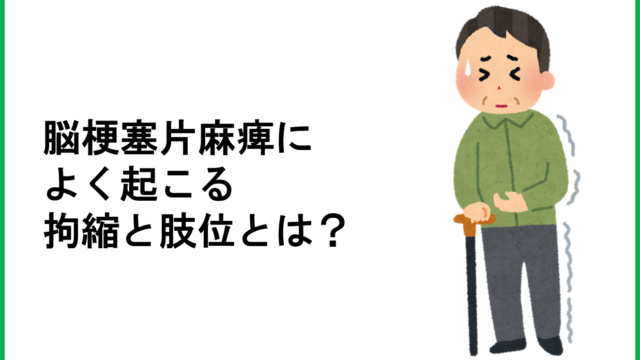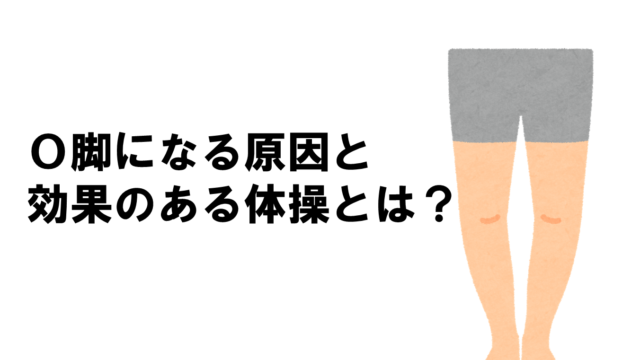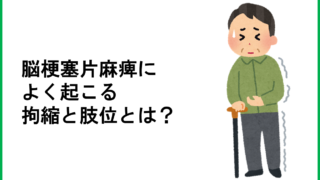車椅子が合っていないと姿勢が崩れ動作が行いにくくなるだけでなく、部分的に体圧がかかり褥瘡や拘縮が発生してしまう可能性が高くなります。
そのため、車いすの選定はとても大切です。

Contents
車椅子の適合基準(合わせ方)は?
車椅子がその人に「合っているか」を確認することは重要です。
車椅子の種類によって多少異なりますが、車椅子にはいくつかの適合基準があります。

シート(座面)の幅
シートの幅は、介助用車椅子と自走式車椅子で適合基準が異なります。
介助用車椅子の場合は、対象者の腰幅(座位臀幅)より4~5cm(左右に2~2.5cmの隙間)程度広いものが良いとされています。
一方、自走式車椅子の場合はハンドリム(タイヤ横の握りて)を握ってこぎやすいように、対象者の腰幅より3~4cm(左右に1.5~2cmの隙間)程度広いものが良いとされています。
座位臀幅とは、臀部の最も幅が広い箇所です。
シートの幅が広すぎると姿勢崩れの原因になりますし、シートの幅が狭すぎると臀部や大腿部が圧迫されてしまいます。
またシートの幅が狭すぎると、移乗介助時の接触や巻き込みなどの事故が起こりやすくなります。
シート(座面)の奥行き
シートの奥行きは、座底長より5~7cm程度短いものが良いとされています。
また介助用車椅子の場合はシートの前から膝窩までの距離を3cm程度とし、足こぎ操作をする方の場合は下肢を動かしやすいように、その距離を若干長くしておきます。
座底長とは、臀部後端から膝窩までの長さです。
シートの奥行きが長すぎると臀部とバックレストの間に隙間が出来てしまい、仙骨座りやずり落ちの原因にもなります。
シートの奥行きが短かすぎてもずり落ちの危険がありますし、大腿部の接触面が少なくなるため臀部への体圧が増えてしまいます。
シート(座面)の高さ
シートの高さは、座位下腿長より5cm程度高いものが良いとされています。
座位下腿長とは、足底から膝窩までの長さです。
足こぎ操作をする方の場合は、シートの高さを通常よりも若干低く設定しておきます。
シートが低すぎると仙骨座りやずり落ちの原因になるだけでなく、立ち上がり動作がしにくくなってしまいます。
バックレスト(背もたれ)の高さ
バックレストの高さは、座位腋窩高より7~10cm程度低いものが良いとされています。
座位腋窩高とは、座面から腋窩までの長さです。
自走式車椅子の場合は、上肢(肩)の動きを制限しないようにバックレストを肩甲骨下角より若干低く設定しておきます。
アームレスト(肘置き台)の高さ
アームレストの高さは、座位肘頭高より2~3cm程度高いものが良いとされています。
座位肘頭高とは、座面から肘までの長さです。
アームレストの位置が高すぎると、肘を置いたときに肩が挙上して窮屈な姿勢になります。また、自走式車椅子の場合、ハンドリムを操作しにくくなってしまいます。
反対にアームレストの位置が低すぎると、肘を置くために前傾姿勢になりやすく体幹の傾斜が起こりやすくなってしまいます。
フットレスト(足置き台)の高さ
フットレストの高さは、座位下腿長に合わせます。
また、大腿部後面とシートとの間に隙間があきすぎていないか、大腿部後面が圧迫されていないかを確認します。
さらに、フットレストから床面までの距離は5cm以上あると良いです。
フットレストの位置が高すぎると膝は必要以上に曲がり、大腿部後面の隙間は大きくなり臀部への体圧が増えてしまいます。
フットレストの位置が低すぎると足底が接地せず、大腿部後面への体圧が増えてしまいます。
おわりに
車椅子の適合・選定で、その対象者の姿勢だけでなく、ADLやQOLまで変わってきます。
そのため車椅子の適合・選定はとても重要です。
しかし、多くの病院や施設では車椅子の種類や数が限られており、対象者に最も適した車椅子に座ってもらうことが困難なケースがよくあります。
そして古くからある通常タイプの車椅子では調節出来るところが少ないため、クッションなどを使用したシーティングが非常に大切になってきます。